メルマガ: 102th 「債券ファンドマイナスの1年 金利をさくっと解説シンガポールか香港か 要因は債券発行と富裕層」
【目次】
1.今週の一言/釣り
2.モノリスの活動日記/サービス改善
3.記事にコメント/本日は債券、金利をさくっと説明
4.経営コラム/シンガポールと香港か
1. 今週の一言/釣り
こんにちは。門垣です。
週末は、海釣りへ。
ありがたいことに晴天に恵まれ、
心躍る気持ちで出港。
少し時間が遅かったので、
大漁とはいえませんでしたが、
大きいお魚も釣ることができ、
リフレッシュできました。
週末は平日以上にPC作業や考えごとする癖があるため、
釣りはデジタルデトックスにもなり、
自然を感じることができて、
素晴らしいなぁと思った一週間でした。

2. モノリスの活動日記/サービス改善
今年も残すところあと2ヶ月と少し。
引き続き、運用助言のマネーコンパス社に関して、
人材採用、デジタル投資、サービス改善を行っています。
来月あたりから、
サービス改善のためのヒアリング目的で、
運用助言のお客様を訪問させて頂き、
お時間を頂ければと思っています。
よろしくお願いいたします。
3.記事にコメント/本日は債券、金利をさくっと解説
米「債券の年」に時間切れ迫る-損失拡大の運用者はポジション見直し
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2023-10-16/S2L9CQT0G1KW01
2023年は債券の年と言われていたが、プロ投資家の間では、最も厳しい1年だったという報道。
記事の中には、約半世紀の間米国経済や政策の分析を行っている81歳のチーフエコノミストのハント氏は、「極めて屈辱的な年になる」と言及し、同社の
米国債ファンドは、年初来のリターンが-13%であった。
世界の債券を運用する機関投資家がベンチマーク指標としている、Bloomberg 世界債券指数の年初来のリターンは10月20日時点で-3.2%。たとえ、運用パフォーマンスが-1%だったとしても、業界の指数基準と比較すると、パフォーマンスは良いと言える数字になっている。
富国生命、金利先高観で下期の円債投資ゼロ-上期はオープン外債増加
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2023-10-17/S2E3V9DWLU6801
富国生命保険が、円金利先高観が強まっていることを背景に、下期は円債への投資をしないことについて言及。一方で、円高にブレる要因もすくないことから、為替ヘッジ付きの外国債券は売却済みで、新規投資資金1,000億円を含めて、ドル建てのヘッジなし外国債券の購入に1,550億円振り向けている。
金利をさくっと解説
通常、金利は期間が長いほど高く、短いほど低い。
これは、当たり前であるが
長期でお金を貸し出すときに、
短期間貸し出すよりも返済のリスクが
高くなるため長期金利を高く設定するからだ。
しかしながら、今は逆の状況だ。
下記のチャート(縦軸金利、横軸期間)をみると、
短期金利の方が長期金利を上回っている。
1年金利は5%を超えているが、
10年金利は5%を下回っている。

(出所:Bloomberg)
この現象を「逆イールドカーブ」
(イールド=利回り カーブ=曲線)と呼ぶが、
景気後退の前に生じる事が多い。
なぜ逆イールドが発生するのであろうか。
インフレ等の理由により、
中央銀行が金融引き締めを実施し、
利上げ(政策金利)を行う。
利上げというのは、米国の場合、米国の民間銀行が連邦準備銀行(FRB)に預けているお金を、
他の銀行に貸し出すときの金利を操作して
(この金利をベースにして)
政策金利を誘導していくことだ。
この事情を織り込んで、債券市場においては、
2年国債等の短期・中期金利は上昇する傾向がある。
つまり短期金利は政府の政策に影響される。
一方で、
長期金利は投資家の動きによって影響を受ける。
利上げを行うと企業は融資を借りにくくなる。
個人も不動産のローンの金利が上昇すると
購入を抑制する。
そうすると機関投資家は、景気減速を予想し、
将来政府が利下げをすることを予想する。
また、長期の金利も下がることを予想し、
比較的金利の高いうちに長期債の購入を検討する。
長期債の購入が増えると、債券価格は上昇し、
逆に利回り(金利)は低くなる。
債券価格と利回りは反比例するからだ。
したがって、
短期金利よりも長期金利は上昇しにくくなり、
逆イールドが発生する。
下のチャートは過去50年の各指標の推移であるが、
白: 米国金利5-30年の差(=30年-5年金利)
青:米国金利2-10年の差(=10年-2年金利)
薄赤の背景:米国景気後退期(リセッション)
ご覧いただけるように、過去50年で米国は、
約10回の気後退(薄赤色)を経験しているが、
青色のチャート(10年-2年金利)が下落した後、
つまり2年金利が10年金利を上回った
1~2年後にはかならず景気後退を迎えている。

(出所Bloomberg)
最後に、逆イールドカーブが発生し、
その1-2年後に景気後退を迎えると、
金融市場はどうなるのであろうか。
先ほどのチャートに下記の指標を加えた。
紫:Bloomberg世界債券総合指数
オレンジ:S&P指数
水色:日経平均指数

(出所:Blomberg)
景気後退期においては、
S&Pと日経平均は大きく下落している。
一方で、債券指数は横ばい。
今後、金融市場は
上記のセオリー通りに動くのであろうか。
みなさんは、どのような運用をされますか?
4.富裕層コラム/シンガポールか香港か
アジアの金融ハブは、シンガポールか香港か。
22年から23年9月にかけて、
日本を除くアジアで発行された債券の大部分は、
中国の金融機関や地方政府系企業だった。
同様に、香港でも金融、不動産セクターの発行が多く、
中国+香港で発行された債券は、
アジアの半分以上を占める。
つまり、中国+香港市場は、
アジアを代表する債券市場国だ。
しかしながら、
今年5月には米製薬会社のファイザーが、
米抗がん剤メーカーのシージェンを買収するための資金をシンガポールの債券市場で調達した。その金額は310億ドル。
ファイザーが発行した債券は
シンガポールの税務当局によって、
適格債務証券(QDS)に認められている。
つまり、この社債から得られる利益について、
投資家に課税されるのはわずか10%ほどだ。
このような制度から、
シンガポールは企業を誘致しており、
国外会社による債券の発行割合は21年は全体の7%、22年は3%であったが、
今回ファイザーが調達した金額は
シンガポールで発行された債券の約59%を占める。
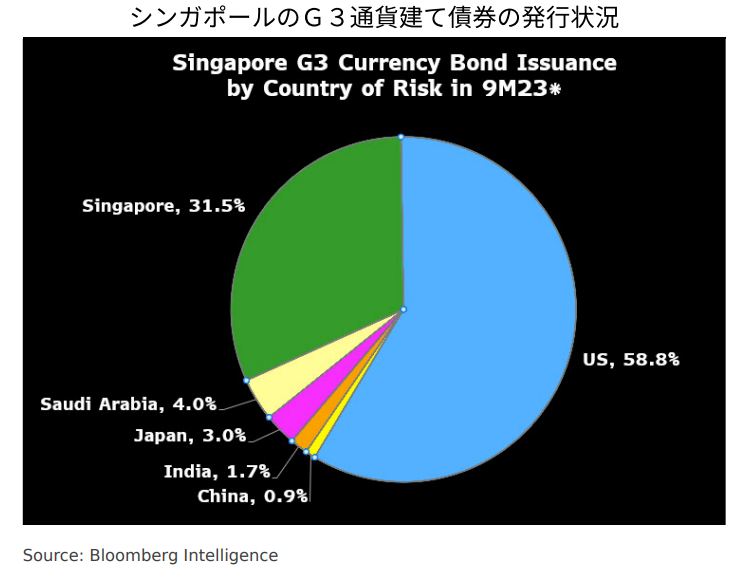
次に、ウェルスマネジメント市場。
つまり、富裕層の資産市場。
両国とも、あらゆる制度で投資家を優遇し、
世界各国の富裕層から富を集めている。
ボストンコンサルティンググループの
レポートによると、
香港のクロスボーダー(海外からの資金)の
富裕層金融資産は21年で2兆3000億ドル、
シンガポールは1兆5000億ドルと香港がシンガポールを上回る。ちなみに、一番はスイスで、2兆5,000億ドルだ。
しかしながら、
今後の成長率(21年~2026年)をみると、
香港は年平均成長率で8%増加するのに対して、
シンガポールは10%。
シンガポールが追い上げてきている。
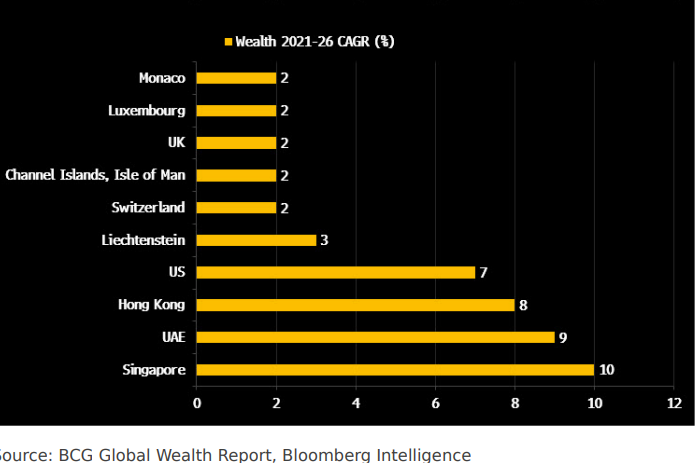
香港は中国から資金流入が一番多いが、
中国政府の政策により、
動きが止まることも多い。
つまり、地政学的リスクだ。
外国為替市場でも、
国際決済銀行(BIS)の調査によると、
22年4月の1日平均出来高はシンガポールが9290億ドル、香港は6940億ドルだ。
現在は、香港が優勢であるが、
将来的にはシンガポールが金融大国に
なるかもしれない。
来月、シンガポールに調査にいってみようと思う。
参考レポート:Bloomberg Intelligence Report
今週も宜しくお願いします。

